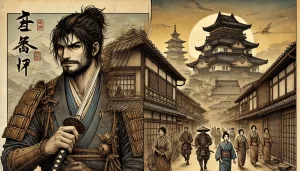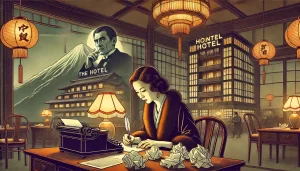「オズの魔法使い」は、アメリカの童話作家ライマン・フランク・ボームによって1900年に発表された児童文学作品です。竜巻によってカンザスから不思議なオズの国へ飛ばされた少女ドロシーが、故郷に帰るために繰り広げる冒険物語は、世界中で愛されています。 本記事では、「オズの魔法使い」のネタバレを含むあらすじから、登場人物、そして物語に隠された意味まで徹底解説していきます。
「オズの魔法使い」のネタバレ!
竜巻に巻き込まれて愛犬トトと共にオズの国へ飛ばされた少女ドロシーは、帰郷を願ってエメラルドの都に住むオズの魔法使いに会いに行きます。
道中、脳が欲しいカカシ、心優しいブリキの木こり、勇気が欲しい臆病なライオンと出会い、共に旅をすることになります。 西の悪い魔女を倒せば願いを叶えると魔法使いに言われたドロシーたちは、困難を乗り越え魔女を倒しますが、魔法使いはただのペテン師でした。
それでも知恵を絞って仲間たちの願いを叶えた魔法使いは、ドロシーと共に気球でカンザスへ帰ろうとしますが、ドロシーは気球に乗り損ねてしまいます。
落胆するドロシーでしたが、南の良い魔女に銀の靴の魔力について教えられ、その力を使って無事にカンザスへ帰ることができました。
「オズの魔法使い」の概要
「オズの魔法使い」は、ライマン・フランク・ボームによって書かれた、1900年出版の児童文学作品です。鮮やかなカラー挿絵が革新的だったこの作品は、たちまち人気となり、アメリカで最も愛されるおとぎ話と言われるほどになりました。 カンザスに住む少女ドロシーが、竜巻によって不思議なオズの国へ飛ばされ、そこで様々な仲間と出会いながら冒険を繰り広げ、最終的に故郷へ帰るという物語です。 この作品は、単なる冒険物語としてだけでなく、当時のアメリカの社会状況を反映した寓意が含まれているという解釈も存在します。
「オズの魔法使い」の登場人物
ドロシー:ジュディ・ガーランド
主人公。竜巻によってカンザスからオズの国へ飛ばされた少女。故郷に帰ることを切望している。 ジュディ・ガーランドは、1939年公開の映画「オズの魔法使い」でドロシー役を演じた女優。
カカシ:レイ・ボルジャー
脳が欲しいと願うカカシ。ドロシーの最初の旅の仲間。 レイ・ボルジャーは、映画「オズの魔法使い」でカカシ役を演じた俳優・ダンサー。
ブリキの木こり:ジャック・ヘイリー
心が欲しいと願うブリキの木こり。心優しい性格。 ジャック・ヘイリーは、映画「オズの魔法使い」でブリキの木こり役を演じた俳優・歌手。
臆病なライオン:バート・ラー
勇気が欲しいと願う臆病なライオン。仲間思い。 バート・ラーは、映画「オズの魔法使い」で臆病なライオン役を演じた俳優・コメディアン。
オズの魔法使い:フランク・モーガン
エメラルドの都に住む偉大な魔法使い。ドロシーたちの願いを叶える力を持つとされている。 フランク・モーガンは、映画「オズの魔法使い」でオズの魔法使い役を演じた俳優。
西の悪い魔女:マーガレット・ハミルトン
オズの国を支配する邪悪な魔女。ドロシーたちの前に立ちはだかる。 マーガレット・ハミルトンは、映画「オズの魔法使い」で西の悪い魔女役を演じた女優。
東の悪い魔女
マンチキンを支配する悪い魔女。ドロシーの家が落ちてきて死んでしまう。
北の良い魔女
ドロシーを助けてくれる良い魔女。
南の良い魔女:ビリー・バーク
ドロシーに銀の靴の魔力について教える良い魔女。 ビリー・バークは、映画「オズの魔法使い」で南の良い魔女役を演じた女優。
「オズの魔法使い」のあらすじと結末
竜巻に巻き込まれて
アメリカのカンザス州でエム叔母、ヘンリー叔父と暮らす少女ドロシーは、愛犬トトを連れて竜巻に巻き込まれ、家ごと不思議なオズの国へ飛ばされてしまいます。
仲間との出会い
オズの国で、脳が欲しいカカシ、心優しいブリキの木こり、勇気が欲しい臆病なライオンと出会い、ドロシーは彼らと共にエメラルドの都を目指す旅に出ます。 途中、西の悪い魔女の策略によって幾度となく危機に陥りますが、知恵と勇気を合わせて乗り越えていきます。
魔法使いの正体
長い旅の末、ようやくエメラルドの都に辿り着き、オズの魔法使いに会ったドロシーたち。 しかし、魔法使いはカンザスから迷い込んだただの老人で、魔法使いではなくペテン師だったのです。
銀の靴の魔力
落胆するドロシーでしたが、南の良い魔女グリンダに会い、銀の靴の魔力を使って故郷に帰れることを知ります。 かかとを3回鳴らして「家へ帰りたい」と唱えると、ドロシーは愛犬トトと共にカンザスの家へ戻ることができました。
まとめ
「オズの魔法使い」は、子供から大人まで楽しめる、普遍的な魅力を持った作品です。 ドロシーの冒険を通して、友情、勇気、知恵の大切さを教えてくれます。 また、単なるおとぎ話としてだけでなく、当時のアメリカの社会状況を反映した寓意が含まれているという解釈もあり、様々な視点から読み解くことができます。